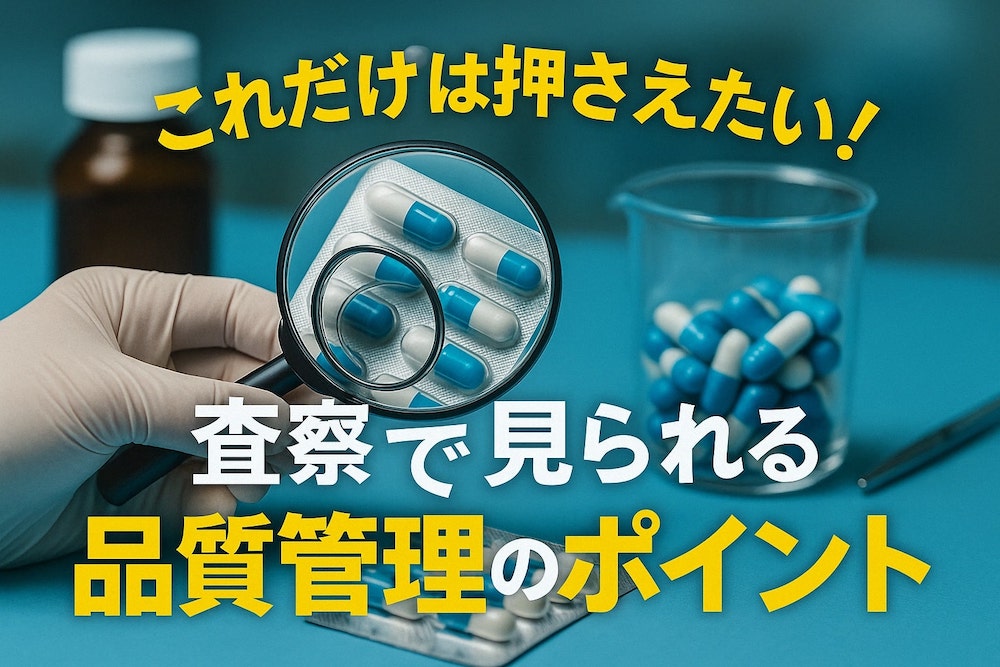これだけは押さえたい!査察で見られる品質管理のポイント
- Published
- in ビジネス
品質管理部門にとって「査察」という言葉は、緊張感と責任が伴う重大イベントです。
特に医薬品業界では、GMPに基づく査察が製品の品質保証において最も重要な関門の一つとなっています。
しかし、多くの現場担当者は「何を準備すべきか」「査察官は本当は何を見ているのか」という点で不安を抱えているのではないでしょうか。
私自身、食品メーカーから製薬会社への転職を経て、両業界での査察対応経験があります。
その中で痛感したのは、「現場の言葉」と「規制当局の言葉」の間には大きな溝があるということです。
本記事では、その架け橋となるべく、査察で本当に見られるポイントを現場目線で解説します。
この記事を読むことで、査察に対する漠然とした不安が具体的な準備項目に変わり、自信を持って査察に臨むためのヒントが得られるでしょう。
単なる対策ではなく、日常業務の中で自然と査察準備ができる体制づくりこそが、本当の品質管理だと思います。
査察の基本理解と全体像
査察の種類と目的:GMP査察・定期査察・抜き打ち査察
査察にはいくつかの種類があり、それぞれ目的や特徴が異なります。
まず「GMP査察」は医薬品の製造管理・品質管理が適切に行われているかを確認するためのものです。
製造所の許可を得る際や更新時に行われ、特に海外展開を考える企業にとっては、PIC/S GMPへの対応も重要課題となっています。
「定期査察」は通常2〜3年ごとに実施され、前回からの改善状況や継続的な管理体制が焦点となります。
事前通知があるため準備時間はありますが、その分、より詳細な確認が行われることを想定すべきです。
一方、「抜き打ち査察」は文字通り予告なしで行われ、日常的な管理状態を見るものです。
特に品質トラブルの情報がある場合や、特定の懸念事項が浮上した際に実施されることがあります。
査察官の視点を理解する:質問傾向と注目ポイント
査察官は単に規制への適合性だけでなく、「その会社が品質を本当に重視しているか」という文化的側面も見ています。
私が実際に対応した査察では、表面的なドキュメントチェックより「なぜそうしたのか」という判断理由を問われることが多かったです。
査察官がよく確認するポイントとして:
- 経営層の品質へのコミットメント(予算、人員配置など)
- 品質方針の現場への浸透度
- 問題発生時の対応速度と透明性
- データの信頼性と完全性
特に注目すべきは、査察官は「完璧な会社」を期待しているのではなく、「問題を発見し改善できる会社」を評価する傾向があるということです。
よくある指摘事項の傾向分析(現場データから)
私が過去5年間で収集した査察データによれば、指摘の約40%は「記録の不備」に関するものでした。
特に手書き記録での修正方法、電子記録のバックアップ体制、変更履歴の管理などが上位を占めています。
次いで多いのが「逸脱管理の不備」で約25%。
逸脱の定義があいまい、是正措置の効果検証が不十分、再発防止策が形骸化しているなどの指摘です。
また意外に多いのが「教育訓練の形骸化」に関する指摘で約15%。
特に教育の有効性評価や力量確認の方法について、具体性を求められるケースが増えています。
これらの指摘は、実は日常業務の中で小さな改善を積み重ねることで大幅に減らすことができるものばかりです。
査察で見られる品質管理の主要ポイント
原料受け入れから出荷までのトレーサビリティ
1. 原料受入時の確認ポイント
- 規格書との整合性確認手順
- サプライヤー評価の定期実施
- 原料ロット管理とサンプル保管
2. 製造工程での追跡管理
- 中間品の保管条件と使用期限
- 工程内試験の判定基準と記録
- 製造指図書と製造記録の整合性
3. 最終製品の出荷判定プロセス
- 出荷判定会議の運営方法
- 市場出荷後の安定性モニタリング
- 顧客クレーム情報のフィードバック体制
査察では、特定のロットを選定し、原料から最終製品までの一連の流れをたどる「トレーサビリティ査察」が行われることがあります。
どの時点でも製品の状態と責任者を特定できる体制が必要です。
私の経験では、特にロット番号の管理方法と使用期限の設定根拠について詳細な質問を受けることが多かったです。
記録類の整合性とリアルタイム記録の重要性
記録は製薬業界の品質管理における「証拠」です。
どれほど素晴らしい管理をしていても、それを証明する記録がなければ「実施していない」と同じ扱いになりかねません。
記録における重要なポイントは:
- リアルタイム性:作業終了後にまとめて記録するのではなく、作業と同時に記録する習慣づけ
- 整合性:複数の記録間で矛盾がないこと(例:製造指図書と実際の製造記録)
- トレーサビリティ:誰が、いつ、何を行ったかが明確であること
- 修正の適切性:誤記入があった場合の修正方法(二重線、日付、サイン)の統一
記録修正の適切な方法
✅ 誤った部分に二重線を引き
✅ 正しい情報を記入し
✅ 修正者のイニシャルと日付を記入する
❌ 修正液や修正テープは使用しない
❌ 元の記録が読めなくなるような修正はしない
❌ 後日まとめて修正しない
「記録のための記録」ではなく、「プロセスを改善するための記録」という意識が大切です。
異常・逸脱管理:その場対応と事後の記録
製造現場では予期せぬ異常や逸脱が発生するものです。
査察では「問題がないこと」ではなく「問題への対応が適切であること」が評価されます。
「異常の発生は必ずしも悪いことではない。しかし、同じ異常を繰り返すことは明らかに悪いことである」
異常・逸脱管理において重要なのは:
- 速やかな一次対応と報告体制
- 根本原因分析(RCA)の徹底
- 効果的な是正措置・予防措置(CAPA)の実施
- 類似工程への水平展開
- 対策の有効性評価と定期的なレビュー
特に「根本原因分析」については、表面的な原因だけでなく、なぜそれが起きたのかを掘り下げて考える「5つのなぜ」などの手法を活用することが効果的です。
教育訓練と力量評価:形式だけではNG
査察官が最も関心を持つ項目の一つが「教育訓練」です。
特に近年は、単なる教育実施の記録だけでなく「その教育が効果的だったか」の評価方法についても問われるようになりました。
効果的な教育訓練のためのポイント:
- 教育内容の階層化(基本→応用→専門)
- 理解度確認の多様化(筆記テスト、実技評価、ディスカッション)
- OJTとOff-JTの適切な組み合わせ
- 定期的な再教育の仕組み
- 品質文化の醸成(なぜその手順が必要なのかの理解促進)
私が実際に導入して効果のあった方法として、「教える側になる」機会を設けることがあります。
例えば中堅社員に新人教育を担当させることで、自分自身の理解も深まり、手順の本質的な理解につながりました。
変更管理と文書管理:小さな変更も査察対象に
変更管理は「計画的な変化」を管理するための重要なシステムです。
しかし多くの企業で「何が変更に該当するのか」の線引きがあいまいで、トラブルの原因となっています。
変更管理の対象となる例:
- 製造機器の更新や移設
- 原料サプライヤーの変更
- 製造方法や試験方法の変更
- 規格値や判定基準の変更
- システムやソフトウェアの更新
重要なのは、変更前後のリスク評価と検証が適切に行われているかという点です。
特に患者安全性や製品品質への影響評価は必須であり、「変更後の確認」も計画的に実施する必要があります。
また文書管理については、以下の点に注意が必要です:
- 文書階層の明確化(方針→規程→手順書→記録様式)
- 改訂履歴の管理と旧版の適切な廃棄/保管
- 文書配布・回収の記録
- 定期的な文書レビューの実施
「小さな変更だから」と変更管理の手続きを省略すると、それが査察での重大な指摘につながることがあります。
特に「なぜ変更管理の対象としなかったのか」という判断根拠を問われるケースが増えています。
査察前の準備と”現場力”の高め方
品質部門だけでなく「全社的な巻き込み」のすすめ
査察対応は品質部門だけの仕事ではありません。
製造、研究開発、保管・物流、営業、さらには経営層まで、全社的な取り組みが必要です。
効果的な全社巻き込みのためのアプローチ:
(1)経営層の品質へのコミットメント表明
- 品質方針の策定と周知
- 品質目標の設定と評価
- 必要なリソース(人員・予算)の確保
(2)各部門の役割明確化
- 部門別の品質責任者(QA担当)の任命
- 部門間のコミュニケーション促進
- クロスファンクショナルな品質会議の定期開催
(3)品質文化の醸成
- 小さな改善の継続的実施
- ヒヤリハット情報の共有と活用
- 良い取り組みの表彰や評価
私の経験では、「査察対応チーム」を結成し、定期的な進捗確認ミーティングを行うことで、部門間の連携が格段に向上しました。
初めは「余計な仕事が増えた」という反応もありましたが、次第に「自分たちの業務の質が上がる」という認識に変わっていったのは印象的でした。
模擬査察・ロールプレイの活用術
実際の査察を想定した模擬査察(モックインスペクション)は、準備状況を確認する上で非常に効果的です。
模擬査察を効果的に実施するためのポイント:
- 外部コンサルタントなど第三者の視点を取り入れる
- 実際の査察と同じ時間配分・範囲で行う
- 回答者だけでなく記録係も配置して振り返りに活用
- 弱点を見つけることが目的であり、「できていないこと」を責めない
- 指摘事項に対する改善計画を立案し、実行する
特にロールプレイでは、以下のようなシナリオを想定しておくと良いでしょう:
想定シナリオ例
- 製造記録に不備が見つかった場合の対応
- 査察官が予定外の場所の確認を希望した場合
- その場で回答できない質問を受けた場合
- 過去の指摘事項に対する改善状況の説明
- 最新のガイドライン対応について問われた場合
実際の査察では予期せぬ質問も多いため、「わからない場合の対応」も練習しておくことが重要です。
査察対応者の選定とロジ対応の工夫
査察対応者の選定は査察成功の鍵です。
必ずしも役職が高い人や経験年数が長い人が適任とは限りません。
理想的な査察対応者の条件:
- 担当業務に関する深い知識と理解
- 質問の意図を正確に理解する聞く力
- 簡潔かつ正確に回答する表現力
- プレッシャー下でも冷静さを保てる精神力
- 適切に「わからない」と言える謙虚さ
また、査察当日のロジスティクス対応も重要です。
査察当日のロジスティクス確認事項
- 査察官の動線確保(専用駐車場、入退場手続き)
- 査察会場の環境整備(適切な広さ、温度、照明)
- 必要書類の事前準備と索引作成
- 休憩・食事スペースの確保
- 通訳が必要な場合の手配
- 緊急時の連絡体制
小さなことですが、査察官にとって快適な環境を整えることで、査察全体のトーンが良い方向に向かうことも少なくありません。
言い回しに要注意!査察時の”伝え方”のコツ
査察では「何を言うか」だけでなく「どう言うか」も非常に重要です。
不適切な言い回しが思わぬ誤解や追加質問を招くことがあります。
避けるべき言い回し
❌ 「多分~だと思います」→あいまいな表現は避ける
❌ 「通常は~しています」→例外があることを示唆してしまう
❌ 「今までそれで問題ありませんでした」→科学的根拠が薄い
❌ 「担当者が休みなので」→体制の脆弱性を示してしまう
❌ 「規制が厳しすぎて」→コンプライアンス意識の低さを示唆
効果的な言い回し
✅ 「当社の手順書では~と規定しています」
✅ 「~という理由から、このアプローチを選択しました」
✅ 「~のエビデンスに基づいて判断しています」
✅ 「確認して正確にお答えします」
✅ 「リスク評価の結果、~と判断しました」
特に質問の趣旨がわからない場合は、「質問の趣旨を確認させてください」と明確化を求めることが大切です。
また、「わかりません」と答える場合も、「確認してご回答します」という前向きな姿勢を示すことが重要です。
トラブルを防ぐためのリスクベースアプローチ再考
現場視点で読み解くリスクの洗い出し
リスクベースアプローチは規制当局が推奨する考え方ですが、実際の現場では「どう実践するか」に悩むケースが多いです。
重要なのは、「理論のための理論」ではなく、現場の実態に即したリスク評価です。
効果的なリスク洗い出しのポイント:
(1)多様な立場・経験からの意見収集
- 現場作業者からベテラン管理職まで幅広い視点
- 品質部門だけでなく製造・開発・物流など複数部門の参加
- 可能であれば社外の専門家も交えた議論
(2)過去トラブルの徹底分析
- 自社の過去事例の整理・分類
- 業界内の類似事例の収集
- 潜在的な「ヒヤリハット」情報の活用
(3)プロセスの可視化
- フロー図やPFD(Process Flow Diagram)の活用
- 各工程の入出力とパラメータの明確化
- 管理ポイントとモニタリング方法の特定
私が実践している方法として、「リスクウォークスルー」があります。
実際の製造現場を一工程ずつ歩きながら「ここで何が起こり得るか」を多職種チームで議論する方法で、机上では気づかないリスクが発見できることが多いです。
「リスクアセスメント」の実践的な進め方
リスクアセスメントは「形式的な文書作成」で終わらせるのではなく、「実際の改善につなげる」ことが重要です。
リスクアセスメントの基本ステップ
1. リスクの特定
- ブレインストーミング
- チェックリストの活用
- FMEA(故障モード影響解析)の実施
2. リスクの分析と評価
- 発生頻度(F)の評価
- 重大性(S)の評価
- 検出可能性(D)の評価
- リスク優先数(RPN = F×S×D)の算出
3. リスク低減策の検討
- 設計によるリスク低減
- 予防的管理策の導入
- 検出システムの強化
4. 残留リスクの評価
- 対策後のリスク再評価
- 受容可能性の判断
- 定期的な再評価計画の策定
特に重要なのは、「誰が見ても同じ評価になる」ための基準作りです。
発生頻度や重大性の評価基準を具体的に定義し、主観による評価のばらつきを最小化することが必要です。
不具合事例に学ぶ:過去トラブルからの学びと教訓
品質管理において「失敗から学ぶ」ことは非常に重要です。
自社の過去トラブルだけでなく、業界内の不具合事例からも多くの教訓を得ることができます。
効果的な事例学習の進め方
(1)事実関係の整理
- 何が、いつ、どこで、どのように起きたか
- 発見のきっかけと初期対応
- 影響範囲と被害状況
(2)根本原因分析
- 直接原因と間接原因の区別
- 技術的要因と人的要因の特定
- システム的・組織的要因の考察
(3)対策と効果検証
- 短期的対策と長期的対策の区別
- 対策の有効性評価の方法
- 類似工程への水平展開
(4)組織的学習への展開
- 事例の教育教材への活用
- 標準作業手順書への反映
- 定期的な振り返りの仕組み化
実際の事例からは、単なる「対策」だけでなく、「なぜその問題を事前に予見できなかったのか」という視点も重要です。
特に「ヒューマンエラー」と片付けるのではなく、「なぜそのエラーが起きやすい環境だったのか」を掘り下げることで、真の改善につながります。
Q&Aセクション
Q1: 初めての査察で最も注意すべきポイントは何ですか?
A1: 初めての査察で最も重要なのは「正直であること」です。
わからないことを取り繕おうとして不正確な情報を提供することは、査察官の信頼を著しく損ねます。
わからない質問には「確認して回答します」と伝え、後で正確な情報を提供する姿勢が大切です。
また、事前準備として自社の品質システムの全体像を把握し、特に重要な文書(品質マニュアル、組織図、主要な手順書など)は内容を十分理解しておくことが必要です。
Q2: 査察での指摘事項への対応期限はどのように設定すべきですか?
A2: 指摘事項への対応期限は、まず指摘の重大度に応じて優先順位をつけることが重要です。
致命的な不備(Critical)は即時対応、重大な不備(Major)は1〜3ヶ月以内、軽微な不備(Minor)は3〜6ヶ月以内が一般的な目安です。
ただし、単に期限内に「対応完了」とするのではなく、真の改善につながるよう根本原因分析を行い、適切な対策を講じることが重要です。
対応計画を立てる際は、具体的なマイルストーンと責任者を明確にし、進捗管理の仕組みも併せて構築することをお勧めします。
Q3: 小規模な製薬会社でも効果的な品質管理体制を構築するコツはありますか?
A3: 小規模な製薬会社でこそ、効率的で実効性のある品質管理体制が重要です。
まず「選択と集中」の考え方で、リスクの高い工程や製品に資源を集中させることです。
また、外部リソース(コンサルタントや業界団体)を賢く活用することも一つの方法です。
特に重要なのは、過度に複雑なシステムを導入するのではなく、「シンプルで確実に実行できる仕組み」を作ることです。
例えば、複雑な電子システムよりも、適切に設計された紙の記録システムの方が効果的なケースもあります。
バリデーションやキャリブレーションについては、専門企業のサポートを受けることも検討すべきでしょう。
「【日本バリデーション・テクノロジーズ株式会社】一般事務の求人情報」などを見ると、同社は2002年設立以来、医薬品溶出試験機や物性評価装置の輸入販売、バリデーション/キャリブレーションサービスを提供しています。
越谷テクノオフィスを中心に御堂筋三井ビルや日本橋本町にも拠点を構え、多拠点体制で迅速な技術サポートを行う体制は、小規模製薬会社にとって心強い存在といえるでしょう。
小規模組織の強みは「変更の柔軟性」と「コミュニケーションの密度」なので、これを活かした改善活動を継続することが成功の鍵となります。
まとめ
査察対応は一朝一夕に身につくものではなく、日々の品質活動の積み重ねが試される場です。
本記事で解説した内容を踏まえ、特に押さえておきたいポイントを整理しました。
- 査察は「対策」ではなく「日常の延長」として捉える姿勢が重要です。
- 記録の整合性とリアルタイム性は、品質システムの信頼性の基盤となります。
- 異常・逸脱への対応は「隠す」のではなく「学ぶ」という視点で取り組むことが大切です。
- 効果的な教育訓練は、形式的な実施記録ではなく「理解度の確認」と「現場での実践」にこそ価値があります。
- リスクベースアプローチは「理論」ではなく「現場の実態」に即して実践することで真価を発揮します。
品質管理の本質は「患者さんの安全を守ること」にあります。
規制遵守は目的ではなく、その目的を達成するための手段の一つに過ぎません。
査察対応に追われるのではなく、日々の業務の中で品質文化を育み、継続的改善のサイクルを回し続けることが、真の意味での査察対応力を高めることにつながるのです。
明日から取り組める改善アクションリスト:
1. 記録管理の見直し
- 記録様式の使いやすさチェック
- 記録の保管・検索体制の改善
- 電子記録システムの信頼性確認
2. 教育訓練の強化
- 理解度評価方法の多様化
- OJTの体系化と効果測定
- 教育記録の充実化
3. 変更管理の徹底
- 変更管理対象の明確化
- リスク評価の具体化
- 変更前後の検証方法の標準化
4. コミュニケーションの活性化
- 部門間情報共有の仕組み構築
- 朝礼・終礼での品質情報の共有
- 経営層への定期的な品質報告
5. 現場主導の改善活動促進
- 小さな改善提案の奨励
- 改善効果の見える化
- 優れた取り組みの表彰・横展開
品質管理は「人」が行うものです。
システムや文書だけでなく、「人」を育て、「文化」を育むことこそが、査察に強い組織づくりの本質なのではないでしょうか。